1.ウクライナ侵攻はカーボンニュートラルの転換点か
今さら説明するまでもないが、2021年秋から変調が始まった世界のエネルギー需給と市場は2022年2月のロシアのウクライナ侵攻によって決定的な大混乱期に入った。どの国でも電気料金が1.5~数倍の高騰となり、どの産業、市民もすべてエネルギー価格高騰のダメージを受けている。
唯一の例外はエネルギー資源大国である米国であり、ここではエネルギーの脱ロシアを図る各国向けの液化天然ガス(LNG)増産・輸出の準備が急ピッチで進められている。
今回の混乱は世界的なカーボンニュートラルへの挑戦の動きの最中に起きたものであった。
2021年のグラスゴーでのCOP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)の場で語られた「石炭発電をはじめとする炭素排出の大きな設備を減らし、天然ガスによるコンバインドサイクル発電のような比較的炭素排出の小さい技術をつなぎで使いながら本格的な脱炭素イノベーションを進める」というこの時点での各国のシナリオは、ロシア産ガスの締め出しを図らなければならない現在、大幅な変更を余儀なくされる。
一部には「この情勢を受けてカーボンニュートラルへの動きを世界的なサスペンドにすべきだ」「カーボンニュートラルを掲げることはロシアを利する行為だ」という指摘さえされている。
しかしながらおそらく2022年はカーボンニュートラルの終わりではない。
今から石炭発電の増強をはじめとする炭素排出増加的な手法でエネルギー需給の安定を図ろうとしても、SDGsやESG投資が定着した金融市場では投資資金を集めることは困難だし、カーボンニュートラルを宣言している各国政府も当然資金の出し手とはなりえない。
この点について、5月20日に電気新聞が主催した「カーボンニュートラルニュートラル2050アウトルック」の記念イベントにおいて、日本のカーボンニュートラルのオピニオンリーダーの一人である山地憲治・地球環境産業技術研究機構(RITE)理事長は次のように語っている。
「エネルギー・環境では常にS(安全)+3E(Energy Security 自給率・セキュリティ、Economic Efficiency 経済効率性、Environmental suitability 環境適合性」の同時達成を目指すことが大事だ。2020年あたりからどうもカーボンニュートラルの議論は環境のところだけに論点が偏り過ぎた感があった。
それを機に足が地に着いた形で、かつもともとカーボンニュートラルの意義の一つである国際的化石燃料争奪を消していく、というところに回帰する。つまり、この機会により優れた組み合わせ、進め方のカーボンニュートラルが出てくる、という前向きな意味でこの状況をとらえたい。」
つまり、電気料金の高騰と市場のボラティリティ増加、再エネビジネスのさらなる活況、蓄電池や電気自動車の価格低下や普及、DR(デマンドレスポンス)とVPP(バーチャルパワープラント)の広がりといった動きの中でこれまでの掛け声や企業姿勢のアピール中心ではない本物のカーボンニュートラルチャレンジが、本音のビジネスの世界で始まっていこうとしているのである。
そこで以下、どのようにカーボンニュートラルが進み、どこが焦点なのかについて述べていきたい。
2.供給側と需要側のカーボンニュートラル
言うまでもなくカーボンニュートラルとは二酸化炭素排出を実質ゼロにするという全産業、国民生活にわたる挑戦的な目標である。
カーボンニュートラルに向けての貢献が最も期待されているのが、二酸化炭素排出の多くを占めるエネルギーの脱炭素であり、かつそれは供給側・需要側に整理して考えることができる。
供給側とは、電気に代表されるようにエネルギーを届ける際に二酸化炭素排出の少ない方法をとることを指す。
電力産業やガス産業、さらには石油精製産業の一部はエネルギー統計上「エネルギー転換部門」と呼ばれるが、原子力発電の燃料であるウランを加工した原子燃料や石炭・原油・天然ガスのような化石燃料から、電気・都市ガスやプロパンガス、重油等のエネルギーに転換する部門という意味がある。
そしてこの中で、電気を創り出す原子力発電と再生可能エネルギーである太陽光発電や水力発電、風力発電、地熱発電だけが発電時に二酸化炭素を排出しない、いわゆるゼロカーボン電源である。すなわち、エネルギー供給側のゼロカーボン化とは、原子力と再生可能エネルギーを増やすことに他ならない。
次に図のとおりエネルギーの需要側を見ると、2018年時点で日本で発電用燃料を含めて多く使われているエネルギーは石油製品、すなわち重油、軽油、灯油で全体の37.6%、続いて石炭が25.1%、天然ガスが22.9%と三つ合わせて9割近くになる。今の日本にとってカーボンニュートラルがいかに遠い目標か実感できる数字である。
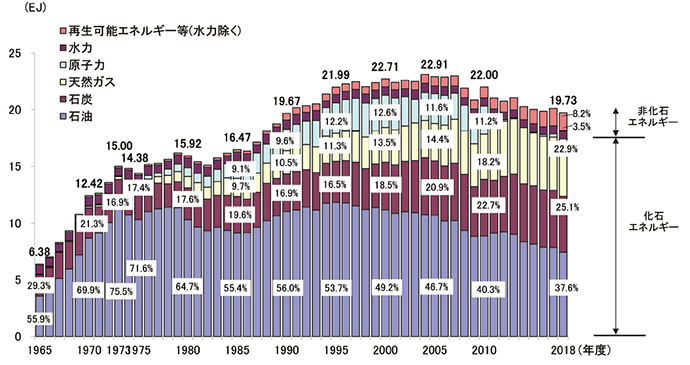 |
|
図 エネルギー需要側のエネルギー内訳 |
そして、今後カーボンニュートラルを目指す上で鍵となるエネルギー需要に占める電化率、つまり最終エネルギー消費の中でゼロカーボン化への進化が期待できる電気が使われている比率は、25.9%となっている。
つまり、今の需要構造では日本国内のすべての電気が原子力、水力、再生可能エネルギーのゼローカーボン電気だったとしても、74%はカーボンニュートラルには向かわないということになる。(化石燃料燃焼をカーボン中立にするメタネーション技術などは2050年までの実現可能性が薄いのでここでは考慮しない)
こうしたケースで、電源側がゼロカーボン化していった後に需要側を電化してその効果を取り込もうとしても、それが成果を産むには時間がかかる。
工場設備や業務用設備、集合住宅のような建物は一度建設されてしまうと設備の償却年数が経過するまでなかなか内容を変えるのは難しいため、2020年代に建てられた二酸化炭素排出の大きなエネルギー設備は数十年にわたってカーボンニュートラルの障害になるのだ。これがカーボンニュートラルのかかわる需要側のロックイン・エフェクトと言われるものであり、だからこそ現在日本政府自ら次々と電化の推進政策を打ち出しているのである。
ところが、現在使っているエネルギー設備を代替設備として電化する場合、当然イニシャルコストが割高である場合が多い。
ロックイン・エフェクトを打ち消すように電化を急ぐとしても、それぞれのユーザーの経済負担、ビジネスの継続性等、持続可能な形で個々のカーボンニュートラルへの取り組みを進めなければ、かえって企業活動の疲弊や脱炭素投資の停滞を招きかねない。これが需要側のカーボンニュートラル推進の難しい点である。
3.技術革新/政策/行動変容の協働
では、カーボンニュートラルに向けた技術革新を供給側・需要側ともにうまく進めていくためには何が必要なのだろうか。
図は、脱炭素にかかわる技術が生まれ、普及し、ユーザー側に浸透して実際にカーボンニュートラルに貢献していくために必要な条件をしめしたものである。
ここでは供給側の再エネ拡大や需要側の電化(給湯器や自動車の電化)、蓄電池導入と活用、DR(デマンドレスポンス)とVPP(バーチャルパワープラント)といった脱炭素技術が既存の技術に代替し、価格革新して社会に普及していくために「技術自体の革新」「それを普及させ、既存技術の代替を後ろ押しする政策」「ユーザーの選択行動、選択基準の変化」の三つが、適切なタイミングで組み合わされ、進んでいく必要性が示されている。
 |
|
図 脱炭素にかかわる技術/政策/行動変容の連動 |
いくら抜本的に脱炭素新技術が発明されても、それが正しい注目を浴びず、それがユーザーに普及するビジネスモデルを誰も作れなければ、それは社会に定着して進化をもたらすことはできない。
かつて日本の優れた電機・電子メーカーは、情報通信とマイクロエレクトロニクスにかかわる世界トップレベルの技術を持っていたし、人々の間でそれらの技術をつないで新しい価値を提供するビジョンは持っていたが、そうしたことが実現されるにはアップルをはじめとする米国のプラットフォーマーの出現を待たなければならなかった。
また、政策だけが突出して高額の補助金を投入しても、例えば日本の太陽光発電の場合、FITの買取単価低落とともに着工が激減し、結果として太陽光発電に対する信任を著しく損ねた結果、現在の自家消費型スキームやPPA(Power Purchase Agreement 電力販売契約)モデルの活況まで立て直しを待たなければならなかった。
特に裾野の広い脱炭素技術である電気自動車や蓄電池の導入、より二酸化炭素排出の少ない商品の選択などは、買い手であるユーザー(個人・企業)の行動変容が何より必要であることは言うまでもない。
そして、技術・政策・ユーザーの行動変容の協働を金融部門が支え、挑戦するベンチャー企業等に継続的に資金が流れ込むようになれば、ようやくカーボンニュートラルへの道が一つ開けることになる。
4.ドラッカーの示唆~イノベーションとは何か
こうした技術革新/政策/ユーザーの行動変容の協働、という脱炭素の進み方を踏まえた時、必要なことは決して新技術の開発だけではないのは自明なことである。
「イノベーション」という言葉を経済学的に「創造的破壊」と定義したのは経済学者・ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター(1883~1950)だったが、その言葉をより実践的な企業経営に持ち込んで多くの言葉で語ったのは「マネジメントを創った男」ピーター・ドラッカー(1909~2005)である。
ドラッカーはマネジメントとは組織内にイノベーションを創り出すことだとし、イノベーションとは今までにないものを産み出すものであると定義した。
脱炭素を社会に広げていく上で参考になるイノベーションの形として、ドラッカーは有名な著作「イノベーションと起業家精神」(1985)の中で、技術革新自体ではないが社会を大きく変容されたイノベーションを2つあげている。
一つ目は、アメリカの貧しい農民に購買力を産み出し、農業全体を革新させたサイラス・マコーミックのイノベーションである。彼が割賦販売を考えつき、収穫収入の不安定を収穫機の販売者がヘッジしたことで、農民たちは過去からの蓄えではなく、未来の稼ぎから収穫機を購入できるようになり、突然、農機具購入のための購買力という資源が生まれた。
二つ目は、チェコの偉大な教育改革者ヨハン・アモス・コメニウスであり、教師の育成、教育学の進歩ではなく、17世紀後半のコメニウスの教科書の発明によって初等教育は圧倒的な進歩をとげた。
教科書がなければ、いかに優れた教師であっても一度に一人か二人の生徒しか教えられない。教科書があれば、平凡な教師でも一度に30人から35人の生徒を教えることができた。
これから使いやすい脱炭素の開発と圧倒的な普及が要求されることを考えれば、必要とされるのは先人たちが成したこの種のイノベーションではないだろうか。ビジネスモデルを作る側の知恵が試されている。
※本記事は作成者個人の意見や感想に基づき記載しています。
※この記事は2022年6月時点の情報に基づき作成しております。

.jpg)



 HOME
HOME  見たい!
見たい!  知りたい!
知りたい!  学びたい!
学びたい!  会いたい!
会いたい! 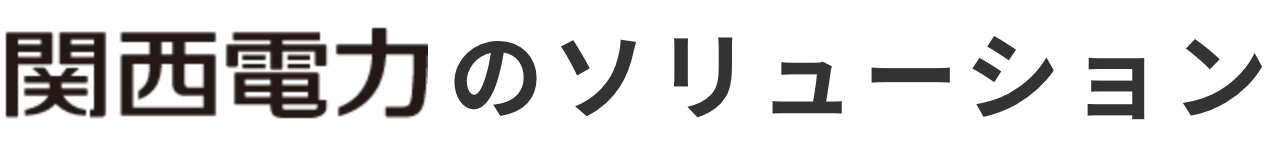
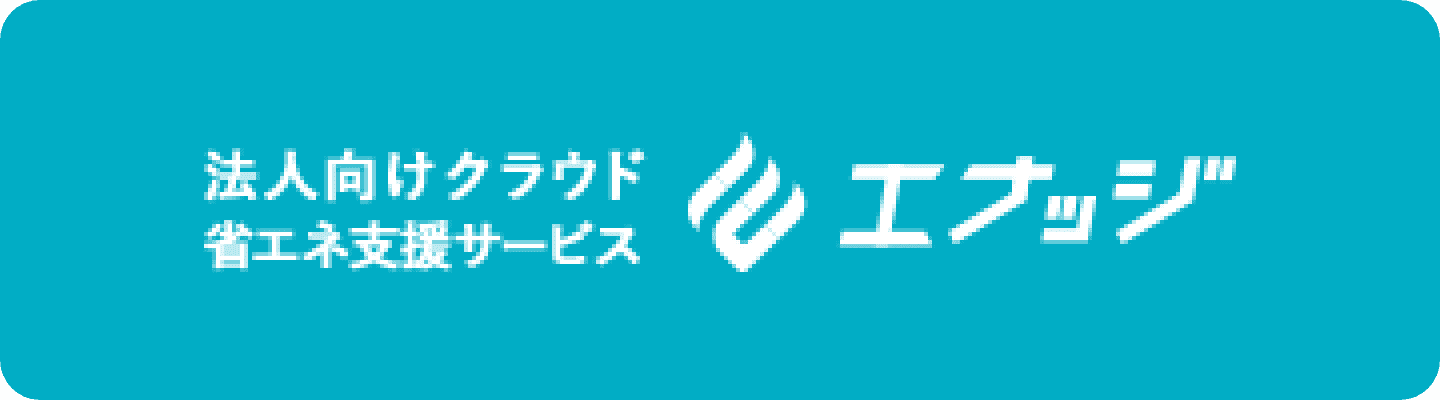
 エナッジ®
エナッジ® 




